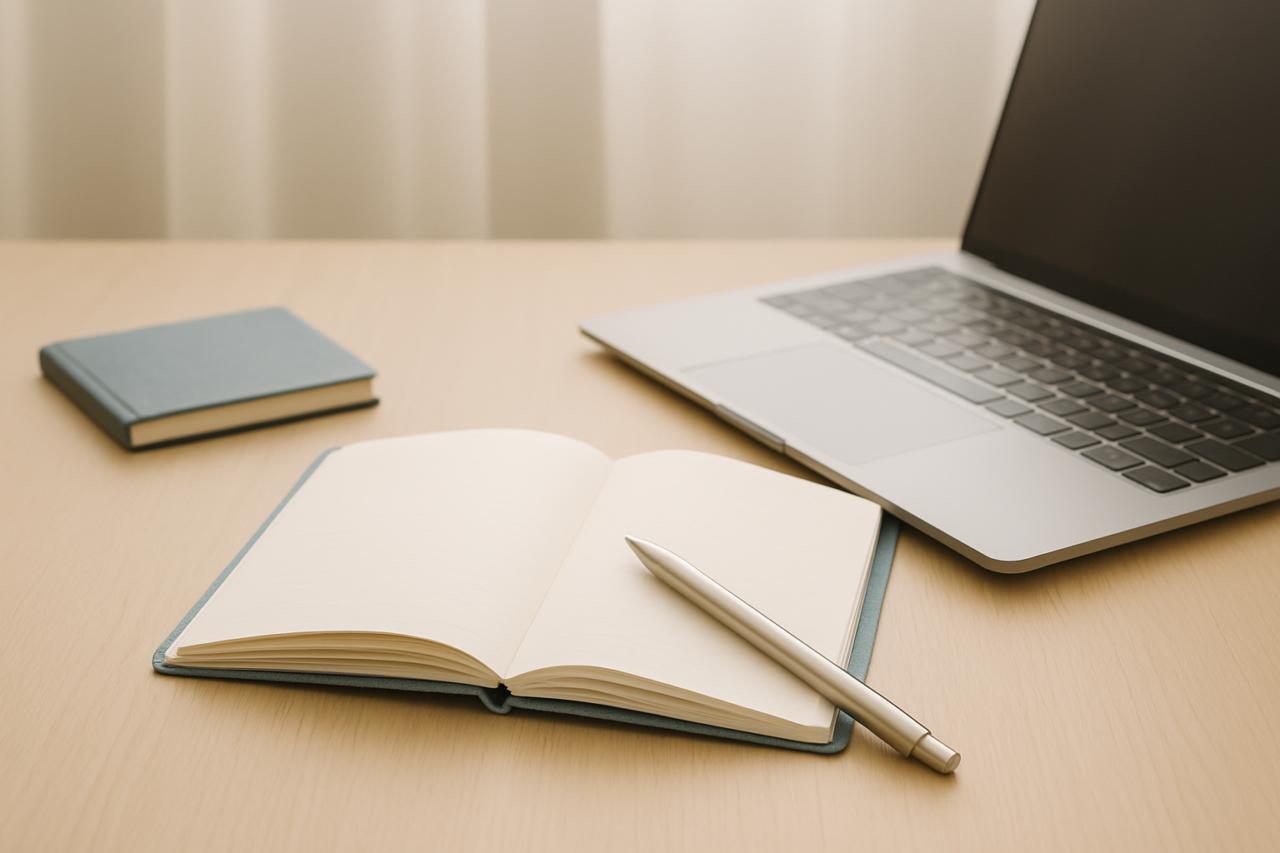スウェーデンから来たソフトマッサージ
看護師が考案したメソッド
タクティールケアは、1960年代に未熟児医療の現場において看護師によって考案されたケア技法です。
看護師による観察と実践により、手で優しく触れることが新生児の体温の安定や体重の増加、成長の促進に効果があることが確認されました。また、母親との愛着形成にも寄与することが認められ、医療現場での有効なケア手法として確立されました。
マッサージ治療の伝統を持つ国、スウェーデン
スウェーデンでは1800年代から、マッサージを治療手段の一つとして捉える考え方が根付いており、19世紀初頭には医師パー・ヘンリックによって医療体操の一部として医療マッサージが体系化されました。これが現在のオイルマッサージの原点とされています。
このような背景のもと、看護師たちは「触れること」が患者の回復に与える影響に注目し、タクティール(触れる)という考え方を基盤としたケア手法を開発しました。
現在、タクティールケアはスウェーデン医療界において補完療法の一つとして認められており、医師が処方する医療的ケアとしても活用されています。
日本における「手当て」の文化
肌と肌が触れ合うという行為は、最も原始的かつ普遍的なコミュニケーション手段の一つであり、日本でも古くから「手当て」として親しまれてきました。
発熱時や腹痛時に、信頼する家族や身近な人から優しく触れてもらうことで、安心感や幸福感を覚えるという経験を持つ方も少なくありません。
しかし、日本社会は「触れること」に対して慎重な傾向があり、近年ではスマートフォンなどによる間接的なコミュニケーションの増加や、ハラスメントへの意識の高まり、新型コロナウイルスの影響なども相まって、肌に触れる行為がますます難しい状況となっています。
このような背景から、人と人とのつながりが希薄化し、孤独感や孤立感の深刻化によって、うつ病などの社会問題にもつながっていると指摘されています。
触れることの重要性
人と触れ合うことは、心身の健康や人間関係の形成に深く関係しています。
人の手の温もりに触れるだけでも心が落ち着きやすくなり、愛情をもって触れられることで、脳内から「オキシトシン(愛情ホルモン)」が分泌され、安心感や幸福感をもたらします。
このような触れ合いは、心の安定に寄与するだけでなく、ストレスの軽減や痛みの緩和にも効果があると言われており、大切に扱われることで自己肯定感を高めることにもつながります。
また、触れるという行為を通じて信頼関係が生まれ、絆が深まり、良好な人間関係の構築にも寄与します。
他のマッサージと異なるタクティールケアの特徴
タクティールケアは、温かい手でやさしく、ゆっくりと、一定の速度とリズムで約10分間触れることにより、「皮膚のC触覚繊維」を刺激し、脳内のオキシトシン(愛情ホルモン)の分泌を促します。
オキシトシンが分泌されると、呼吸が深くゆっくりになり、体が温まり、全身の緊張がほぐれて自然と眠気が生じます。また、オキシトシンの作用により、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑えられ、副交感神経が優位となることで、深いリラクゼーション状態を生み出します。
タクティールケアがもたらすもの
肌と肌の触れ合いによって安心感や穏やかな感情が生まれ、不安やストレスを和らげる効果が期待されます。
触覚や圧覚が痛覚を抑制するメカニズムを活用することで、身体的な痛みの軽減に寄与すると考えられています。
認知症による不穏状態や攻撃的な行動が見られる方に対して、リラックス効果をもたらし、精神的な安定を促す効果が期待されます。
言語によるコミュニケーションが困難な方に対しても、触れることを通じて安心感を与え、信頼関係の構築をサポートします。
手足や背中などに触れることで、自身の身体の輪郭や存在を再認識する感覚を促し、身体認識を高める効果も期待されます。